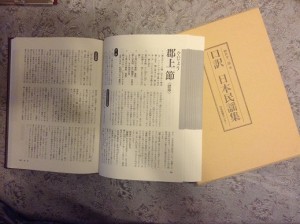昨日、津軽三味線の小山貢山先生のお宅へ行ってきました。
なんで自分の師匠以外の人のところへわざわざ行くの?っていう理由は、CD受け取りに行くため。
(別に師匠も知ってるから、問題ないです)
貢山先生は、以前、初心者向けの楽譜とDVDを出してて、それに沿った内容のCDをお出しになってんですね。
中国にも、ちょっとだけ三味線を触ってみたいっていう人もいまして、そういう人にとっては、(日本自体にはあまり興味のない人、とにかく器楽だけ好きっていう若い人にとっては)わけわからん日本の民謡弾いても楽しくないんで、最適な教材なわけです。
そういう人に頼まれて、買ってきました。
普通にオンラインで買いたい人はここ↓
http://store.shimamura.co.jp/shop/g/g4948667200493/
さて、CD受け取るだけなら、送ってもらえばいいじゃん、というところですが、せっかくだから、日本の筝をちょっとだけ教えてもらいました。
彼は、筝もやってますから。
私は以前、ブログにも書きましたが、私が弾く三味線の音は中国三弦の音色に似てて、私が弾く中国三弦の音は中国の古筝の音色に似てて、私が弾く二胡のピチカートは日本の筝の音色に似てるんですって…
筝を弾けもしない私の音が、何だって人にそう言われちゃうのか、気味悪いと思っていました。
単に、私が日本人であるという思い込み、イメージから、そういう感想を持つ人がいるのか、本当に筝っぽいのか、自分でも知りたくなったんです。
ちなみに、うちは高台に建っているのですが、真下のお宅は生田流の師範の先生のお宅らしく、いつも筝の音が聴こえてます…
しかし、長期にわたって習う気もないのに、ほんのお遊びで触りたいだけなのに、そういうお師匠さんのお家のドアをたたく勇気はなく…
一回だけのお遊びでも全然OKっていう貢山先生にお願いしました。
彼は外国人の日本文化体験レッスンよくやってらっしゃるので、一回だけっていうのも気になさらないようです。
で、たった一回だけのお遊びで、自分の音色の謎が解けたかっていうと…
どうでしょうかねぇ…
同じ弦楽器だからね、似てる音出そうと思えば、出るんじゃないかな~
例えば、中国三弦の曲で、中国の古琴の音を模倣した楽曲って、本当にあるし、実力のある人が弾けば、本当にそういう音するしね。
で、私はたまに無意識に、出ちゃうことが、あるっていうだけではないだろうか。
コントロールして出せるなら、それは技術だけど、私のは単なる偶然だから、話にならない。
余談ですが、弦を押したりするとき、普通に下までえいって押せるので、
「初めての人は、ふつう、そこまでしっかり押せませんよ」と言われてしまいました。
まぁ、私の力持ちぶりは、一門の先生方にバレバレな今日この頃ですからねぇ。
師匠にも、「そんな重い三味線と撥は男でも持つのキツイんじゃなーか」って言われましたし、私の三味線持つたび「おもっ!」って言います(それ言うの、何度目?)。
よくブログにコメントくださるドラゴン先生にも、チューナー改造したとき「女の人で自分でできる人は少ないかも」って言われちゃいましたしねぇ。
でも、世の楽器を弾く女性である程度弾ける人って、日頃、日常生活においては、「できないぶりっ子」してるんじゃないでしょうか、って私は思うんですけど(笑)。