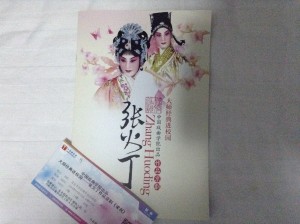
また、関係者の先生からチケットを頂き(^-^)、京劇舞台を聴きに行ってきました。
「京劇なんて、何言ってるか分からないからツマンナイ」なんて言ってたのは、どこの誰よ(笑)ど素人の外国人の私が聴いても感動した!
いえ、別に役者や伴奏者、演出関係者が大学の現役の先生達だから、ヨイショしてるわけじゃないですよ(笑)
結局のところ、主役を演じた張火丁先生が現役の人気京劇役者で、歌が上手いっていうのが最大の魅力なんですよね。
うまく言えないけど、歌い方がドラマチックな気がする(*^o^*)
気になるオケの構成ですが、
普通、昔ながらの舞台だと伴奏者はお客さんに見えない舞台右脇にいるものですし、最近の大型オペラ仕立てですと、ヨーロッパのオペラと同じで床下に入ってしまうものですが…今回は舞台右脇にいるのに、一部の奏者がお客様から丸見え。
で、誰が見えてたのかっていうと、京胡、二胡、三弦奏者の三人。
三弦の馬忠昆先生、京劇三弦というDVD付き教則本を出版してますから、お顔を知ってる人もいると思いますが、カッコいい爺さんですよね〜。
残りの奏者は幕に隠れて見えないけど、月琴、打楽器などの方々がいたと思われます。
ビオラやチェロ、コントラバス、琵琶、笛、箏、笙、阮なんていう方々も、歌の伴奏はしないけど、背景音楽担当としてオケに入っています。
演目は「梁山伯と祝英台」。
ハイ、よく知られた定番ですね。
日本の宝塚でも舞台を平安時代に設定して上演してるくらい有名な中国の民間伝承ですから、大抵の人はご存知かと思いますが、念のためにストーリーをおさらい。
お嬢様の祝英台が男装して都に遊学に出た途中、梁山伯という青年に出会う。
ともに学ぶこと三年、仲良しの二人だけど、英台が女の身であることは秘密。
でも、何となくお互いに恋心を抱いてて、二人とも思い悩んでる。
その後、英台が里に帰る。
梁山伯が会いにいくと英台は馬文才との結婚が決まっていた。
梁山伯は叶わぬ恋を引きずって病死。
英台が嫁ぐとき、梁山伯の墓を通りかかると急に大風が吹く。
英台が墓の前に行くと墓が開き、その穴に身を投げると二匹の蝶(二人の化身)が出てきてひらひらと飛んでいった。
終わり。
演出的にビックリしたのは、やっぱり梁山伯が病死するシーンでしょうね。
英台に許嫁がいると判明後、急に場面が変わって病の床に就く梁山伯。
「英台、英台…」と叫んだかと思ったら、そのまま、バタって死んじゃった。
ええっ、1分も経ってないよ(^^;;
普通、オペラでも歌舞伎でも、死にそうな人って、苦しみながら一曲歌ったり、踊ったりしない?
で、皆して「まだ死なないね」ってイライラするのが定番なのに、この演出は「太快了吧(早すぎだろ!)」と呟く人続出。
でもね、ここを端折ったのも分かるのよ。
だって、ここは適当に済ませて、次の場面、梁山伯の墓の前で、祝英台扮する大スターの張先生にたっぷり歌ってもらいましょうってことなのよ。
たっぷり歌っていただいた後はラスト!
ラストは歌ではなく舞がメイン。
ドライアイスもくもくで、舞台がこの世らしからぬ世界を表現。
大勢の蝶に扮したお姉さんたちがヒラヒラ舞った後は、バックの白い幕が切って落ちて、蝶になった梁山伯と祝英台の登場。
二人で手に手を取って舞ってお終い。
カーテンコールは、お客さん大喜びで総立ち!
みんな、夜も遅いのに、なかなか帰らないから、役者さんは何度も舞台に出てきてご挨拶。
すごいなぁ〜
ある関係者の先生が講義で興味深いこと言ってました。
「伝統芸能って、現代人にとっては面白くない、所詮今の人達に昔のものはわからないと思い込んでて、この何十年も新しいものを創ろうと努力してきたけど、ちょっと方向違いだったんだなぁと最近思うんだよね。数字的に見ても、売れる演目って本当に昔からある演目なのよ。皆がよく知ってるやつ。で、演技や歌が昔の名人にも劣らないものを見せることで、お客さんはちゃんとついてくるんだよね。もちろん、年寄りだけじゃなくて、京劇なんて身近じゃなかった若い子達も、もっと知りたいと興味を持ってくれる。だから、なんだかんだ言って、客の勉強不足を恨むとか、演出家のアイディア不足を問う前に、役者が昔の人に劣らぬ技術を身につけないとね。古いとか新しいとか関係なく、いいもんはいいのよ」
耳があいたた…
京劇役者に限らず、舞台下の10年の練習は舞台上の1分って言いますものね。
