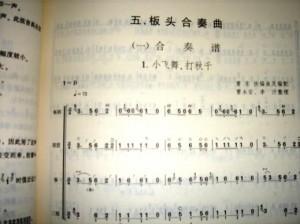どうもお疲れ気味なのか、音が気に触ってしょうがないです(^^;
絶対音感のある人は、風の音やコップがぶつかってコーンと響く音ですら、音名で聴こえて疲れるといいますね。
私は絶対音感ないので、そんなどうでもいい音に疲れることは無いのですが、多少なりとも相対音感はあるらしく、メロディや調がはっきりしているものになると、相対音感に基づく階名が聴こえ始めちゃうんです…
うちのがっこの第二教学楼の防音室は、隣の部屋の音がはっきり聴こえます。
もともと一つの防音室を、後から二人で使えるように真中で二つに区切ったらしく、通常レッスンのあるときは、妨げになるので隣の部屋は学生に貸しません。
で、私はわりと集中力あるので、自分がしっかりしている時は、自分の音以外聴こえないのですが、体調が悪いと隣の部屋の音が聴こえ始め…
そのうち、階名が頭の中をぐるぐる…
芸術系のがっこに在籍している以上、音から逃れられないので、あぁ、疲れる…
そういえば、世の中には無響室ちゅうものがあるらしい。
要するに研究実験用に作られた「無音」の場所。
でも、実際には無音ではないらしい。
というのも、前衛芸術家、ジョン・ケージが言うところによれば、「無音」を聴こうとしてハーバード大の無響室に入ったものの、二つの音、一つは高く、一つは低い音が聴こえるのだそうで、高いほうは神経系が働いている音で、低いほうは血液が流れている音らしいのです。
思うに、少なくとも、自分の心臓の音は聴こえちゃうんでしょうね。
真夜中に静かな場所でも、キーンとか、し~んって響く音、あれ、何なのでしょうね?
もしかして、あれが、神経系の音?
そのようなワケで、無音は生きている以上、不可能なわけです。
(先天的に聴覚障害があって、そもそも、音というものが何か分からないという人の場合はどうなのか、私は専門家じゃないので、よく分かりませんが…)
さて、話が飛びますが、この無響室で音の不可能性をみたという認識が、ジョンケージを「4分33秒」の作曲へ導いたと言われてます。
この曲は、音楽は音を鳴らすものという常識を覆す、「無音の」音楽である。
楽章を通して休止することを示すtacet(オーケストラにおいて、特定の楽器のパート譜に使用されるのが普通である)が全楽章にわたって指示されているので、演奏者は舞台に出場し、楽章の区切りを示すこと以外は楽器とともに何もせずに過ごし、一定の時間が経過したら退場する。
ウィキペディアより引用http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E5%88%8633%E7%A7%92
将来、誰かに「得意な曲は何ですか?」って聴かれたら、「4分33秒」と答えたい…
しかし、ちゃんとしたフォームで4分33秒過ごすのは意外と大変そうだな~